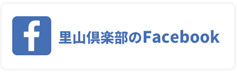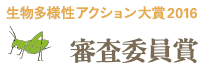1月19日(日)里山と暮らす応援講座 源流の森と棚田編
~炭焼きの準備をしよう~
前回に引き続きの樹木伐採ですが、今回は来月の炭焼き用のクヌギの伐採です。午前の林業についての座学では、昔の里山の景観や現在の林業の課題、海外との比較など、みなさん知らなかったこともたくさんあったようです。午後はしっかり装備を身に付けて斯波さん山へ。西村講師から難しい広葉樹の伐採について、さまざまな林業本職の技の紹介と実演があり、木がどちらに倒れるかの予想で盛り上がりました。倒したクヌギは各自のチェーンソー体験で順番に玉切りにし、枝葉はノコギリとナタでさばいていきます。一日の終わりは、焚き火で焼いた石をお椀に入れて作る山の技の「石焼味噌汁」で身体を温めました。みなさん、次の炭焼きを楽しみにしておられました。
<みなさんの感想より>
・炭=酸素を制限して燃やして炭素のみになったもの という定義にまず目からウロコ!国内の林業を取り巻く環境や経済状況も知らなかった情報でした。石焼味噌汁、知識だけでなく実際やれることが、里山倶楽部の良さですね。
・林業を六次産業とする考え方は興味深かった。機械化がこんなに進んでいることには驚き。道具の多さは用途に合わせているまで理解するものの、現場に運ぶ作業自体が重労働であることを実感した。チェーンソー体験はもっとやりたい。
・「林業=きこり」のイメージが変わりました。林業に大小があることや、北欧での林業、税金や補助金などよい勉強になりました。木を育てるためにかかる年数と携わる人のバランス?がうまく循環しなければいけないと感じました。
・炭の作り方、木の切り方、チェーンソーの口の作り方、ちょうつがいの切り方もわかりやすく、実際に木の始末まで。危険なお仕事びっくりです。最後に石焼味噌汁とコーヒーで体をあたためて、とてもおいしく楽しく過ごせました。
・チェーンソーの使い方・木の切り方:受け口の作り方がよくわかった。ねらったところに木を倒す、山の中で水平に木を切る技術がすごい。道具を使いやすい状態にしておくこと、正しく使うことが非常に重要ということがわかった。
・日本の林業の課題はいっぱいあるけれど、携わる人がしあわせを感じることが一番と思いました。生物多様性のある日本の森は、生活で必要な資源を提供できる能力がある、その価値を見つけ出すことが求められている気がします。
・平坦ではない日本の地形をどのように利用するか、山主に何十年も先を考えてもらうためのヒントがあれば、万博のような外国資材を使うことはなくなるのでは。石焼味噌汁、本当においしかった。ナタの使い方、拾得できた気がします。
・奥山の林業、今昔について、なるほど自分が良いと思うことが大切ですね。炭づくり用の伐採およびチェーンソーの使い方およびノコギリ・ナタ、汗だくになりました。今日は天気が良く、よい一日が過ごせました。
・林業は大変なお仕事だなと思いましたが、なくてはならないお仕事でもあることを知ることができました。命がけでしてくださっていて感謝です。石焼味噌汁はほんとに暮らしの知恵ですね。またやる機会を作ってみたいと思いました。
・江戸時代の里山に木がない!のにおどろき。たくさん木があると思ってました…。林業は死亡率の高さ、第一位とは…。危険と隣り合わせの仕事に感服です。30年たってた木、ありがたく使わせてもらわないとな という気持ちです。
・今回「山の多面的利用」と聞いて、はっとしました!山の目的や役割がかわって今の時代に合う方法でいろんな人たちが集える山が広がればいいな~と思いました。林業にたずさわる西村さんが幸せ!というのが、なにより嬉しいですね。