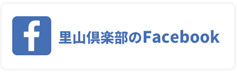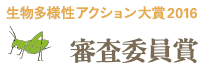2月9日(日)里山と暮らす応援講座 源流の森と棚田編
~炭を焼く!~
大寒波で雪景色となった持尾、心配した車道もなんとか通れて予定どおり、みなさんお待ちかねの炭焼きを行いました。大西講師の指導のもと、3班に分かれて窯からの炭出し・レンガ&粘土の処理・炭の分類と袋詰め・土練り・材の窯詰め・基本講義と、順番に体験していきます。朝は炭を出すことから始めたので、後半の材の詰め方もわかりやすく、班分けすることで、炭焼きにともなう様々な作業も理解しやすかったようです。雪の湿度のせいか思ったよりも顔が真っ黒にならなかったのが少し残念?でしたが、一年間の里山管理のクライマックスとして、みなさん充実した顔の良い一日となりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・炭焼きのクライマックスの炭出しは、たぶんみんなワクワクドキドキなのだと思う。クヌギの木が育って、お茶席で使う菊炭ができあがるまで、何十年という時がかかるなんて、とてもステキなことなんだろう。
・特別にスペシャルな体験、今回は一本の木を育てて山を管理して、切って炭にするという、文字通りの集大成の活動で、春からの活動が一巡したという意味でも感慨深いものがあります。
・初の炭出し、おもしろいですね。終了後は鼻の穴まっ黒でしたが、思ったほどくろくなりませんでした。
・炭焼きの一連の作業はかなりの重労働だと実感しました。木を伐りだして運搬、窯の中に並べるのも、パズルのピースを組み合わせるような、かなり体力のいる作業。昔の人は本当に「えらかった」んだなと。
・炭出し、窯の中は姿勢を変えての作業は難しく、仕込みは木を見極めて並べるのが、はじめはハラハラドキドキしましたが、慣れると足でけとばして詰められるまでになりました。
・全身まっ黒になる覚悟で出席しましたが、鼻の穴まっ黒だけですんだのは良かったのかな?初めての炭づくり、菊炭はまわりがパサパサとれると良品にならないということ、大事に扱わねばと少々キンチョーしながらの袋詰めでした。
・いざ窯の中に入り、大西先生の話を聞くと、炭ができる原理がやっと(?)わかりました。鼻の中までまっ黒で面白かったし、思った以上に腰をつかい、少しきつかった。木を育てる、守る、伐採をする からの炭焼きは大満足です。
・窯の中にすきまなく木を入れるのは難しい作業であった。煙の見方で状態を知るとのことであったが、経験がないと無理ですね。火を入れてみたかった。残念です。
・燃料として最も合理的に考えて、森林の暮らしの一部になっていたんだなと想像がふくらみました。共同作業が多かったので、和気あいあいと楽しい雰囲気でできたことも良い思い出です。
・初めて炭窯を見させていただき、今後、自分で作るときの勉強になりました。土の硬さや木の詰め方など、基本的な体験ができて満足しました。
・山の循環の集大成、炭焼き。やっぱり好きですねー。今度からは薪だけでなく、炭も購入して山を循環させていきたいと思います。いつもながら知識豊かな山男との語らいの時間が嬉しい私です。